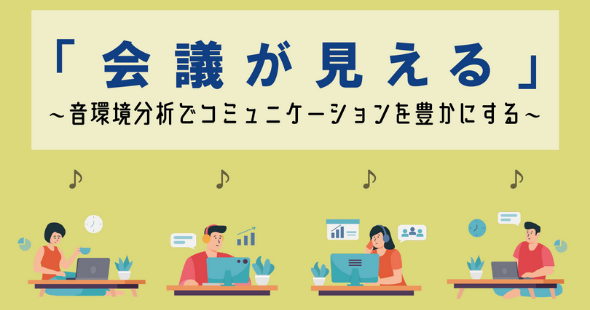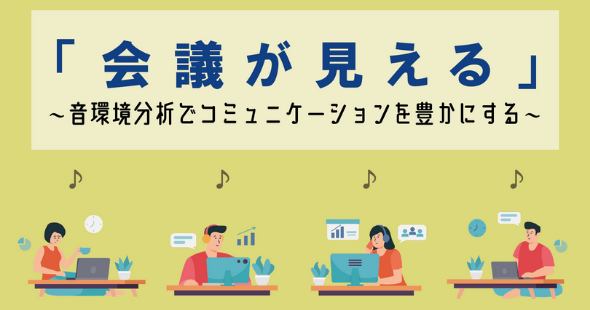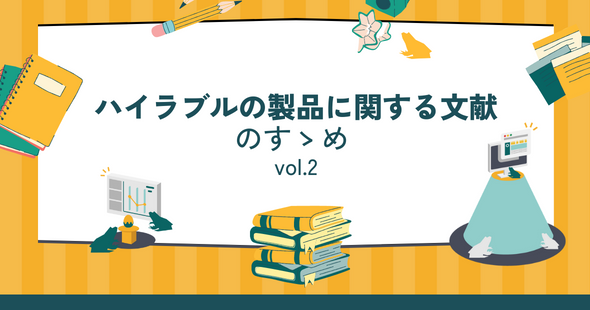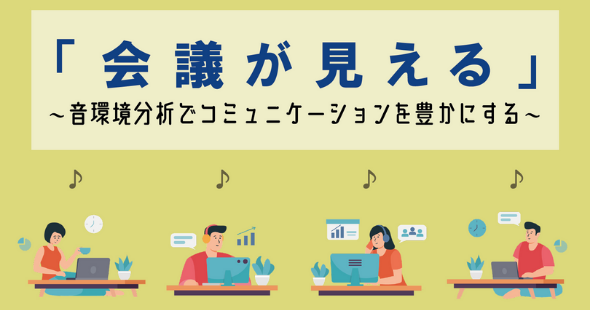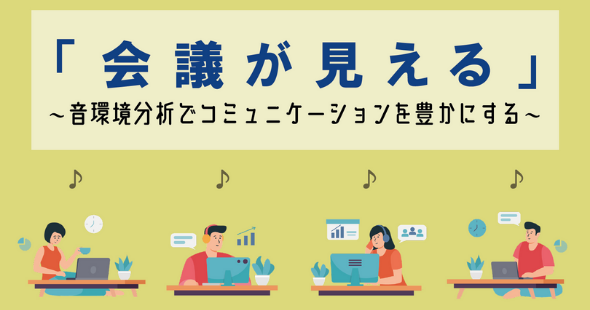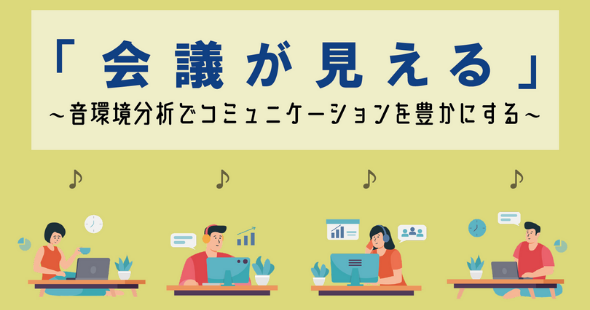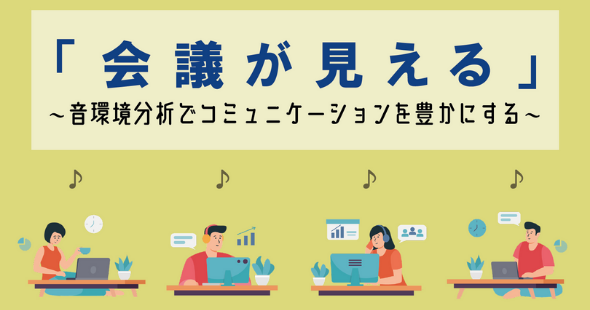現代のビジネスの環境において、コミュニケーションの質の向上は重要である。とくに、対面やオンラインが混ざりあった環境で会議・議論・相談といった日々のコミュニケーションを効果的に行うことの重要性はますます増している。シリーズ「会議が見える〜音環境分析でコミュニケーションを豊かにする〜」では、これまで7万人以上の話し合いを分析してきた音の専門家が会議を解説する。Vol.19 では、コミュニケーションする周辺の音環境に関する最新の研究を紹介する。
本記事は、ニッキンONLINE PREMIUMで連載中の記事の転載です。
※媒体社の許諾のうえ転載しております。
本記事は、ニッキンONLINE PREMIUMで連載中の記事の転載です。
※媒体社の許諾のうえ転載しております。
コミュニケーションする環境の重要性
私たちは日頃、多様な音がある場所で会話をします。たとえば、静かな会議室やざわざわしたカフェ、人の多い居酒屋、あるいは大音量のライブ会場、工事現場などさまざまです。同じ会話をするのだから周囲の環境は関係ないと思うかもしれません。しかし、さまざまな研究で周囲の音環境に強く影響を受けることが示されています。
たとえば、ある研究[1]によると、雑音の音量が大きいほど記憶を必要とする作業に悪影響を及ぼします。とくに、話し声のような意味のある音の場合、小さい音量でも悪影響が出てしまいます。私たちは周囲の音の種類や音量に簡単に影響を受けてしまうのです。
びっくりする音と意思決定
音は意思決定にも影響を与えるという最新の研究を紹介します[2]。この研究で注目したのは「びっくりする音」です。具体的には、6つの同じ高さの音を連続で流すパターンを「通常の音」、最初の5つは同じ高さで最後の6つ目だけを違う高さの音を流すパターンを「びっくりする音」と定めて、「通常の音」を聞いたときと、「びっくりする音」を聞いたときの判断の違いを調べたものでした。実験はポイントを集めるゲーム形式で行われました。ポイントを集めるには、リスクの違う次の2つの方法から選ぶ必要があります。
- ・リスク大:ある確率で高い点数がもらえるが、点数がもらえないこともある
- ・リスク小:確実に少しの点数がもらえる
実験の被験者は「通常の音」と「びっくりする音」のいずれかを聞いた後に、リスクの大小のいずれかの方法を選んでポイントを集めていきました。そして、音のパターンと選んだリスクの大小を比較することで、音のパターンの影響を調べました。
実験の結果は、なんとびっくりする音を聞いた後はリスク大を選択しやすいというものでした。こんな小さな音の違いでも、予測できない音が聞こえてくるとリスクが大きい方を選んでしまうのです。研究では、さまざまな条件で実験を行い、確かにびっくりする音が聞こえたとき、リスク選好型になるということを明らかにしました。こうした判断はおそらく人類が生き残るために必要だったのではないかと推測されています。狩猟を行っていた時代は、知らない音が聞こえたときに、それを探るようなリスクのある行動をしなければ危険な動物や食料の発見ができないからです。
コミュニケーションと周囲の音の影響
これは、コミュニケーションを行う場所の音によって集中力や記憶力だけでなく、判断さえも影響を受けてしまうということを意味します。論文では、都会は車や電車の騒音などびっくりする音で満ちていると指摘しています。都会で会話をすると、無意識のうちにリスクをとるような選択をしているかもしれません。
このことから学べるのは、コミュニケーションを行うときは、周囲の音も考慮した場所選びをするのが重要だということでしょう。じっくり集中して安全な選択をするためには、コミュニケーションを行う場所は静かな場所がよいでしょう。一方でリスクがある決断をするためには、びっくりする音が多い場所が良いかもしれません。
参考文献
- [1] 佐伯ほか 『短期記憶作業時における騒音の影響』日本音響学会誌, Vol. 59, No. 4, pp.209-214, 2003.
- [2] G. W. Feng & R. B. Rutledge, Surprising sounds influence risky decision making, Nature Communications, 15:8027, 2024
ニッキンONLINE PREMIUM 2024年11月2日掲載 (リンク)
🟢お問い合わせ:こちら
#ニッキン #コミュニケーション #音環境 #短期記憶作業 #ハイラブル
この記事を書いたメンバー

水本武志
ハイラブル株式会社代表。カエルの合唱や人のコミュニケーションの研究が専門。 あらゆるコミュニケーションを調べたい。生物研究プロジェクト Project Dolittle もやってます。